今回は江戸時代に日本にやってきたコーヒーについて書いていきたいと思います。
江戸時代までは鎖国政策を取っていたにも関わらず、日本は古今東西の文化の集積地であり続けていました。
それは、いわゆる中央集権社会を形成しなかった事と関係があるかもしれません。
ところで、日本の伝統的なの文化や食の多くは、明治維新以降に脱亜入欧政策に転換した結果、変わっていきました。
日本の風土(含む人)に適した日本の文化や食を再考察し、「心身魂領域を含む広義の意味における健康オタク」を標榜する方々が取捨選択していくヒントになれば良いと考えています。
コーヒーの歴史
ふたつの伝説
飲料としてのコーヒーはアラビア半島の紅海に面したイエメン周辺で始まり、対岸のアフリカ大陸のエチオピアから持ち込まれた習慣であると考えられます。
コーヒーを最初に飲んだのはいすらむ京の修道士とされ、その後、アラビア半島のメッカやメディナなどの都市に広がっていった。
残念なことの一時期、一部の地域においては、為政者によって禁じれらる事もあったとの事です。
コーヒーの歴史・・・ふたつの伝説
コーヒーがいつ、誰によって発見されたかについては有名なふたつの伝説が残されています。
「ヤギ飼いカルディの伝説」:エチオピア
伝説の舞台は9世紀のアラビア半島に程近いアフリカ大陸にあるエチオピアのカッファ地方。
カッファ地方で山羊飼いをしていたカルディ少年は、山羊が赤い実((コーヒーチェリー)を食べたあと、夜も眠らずに飛び跳ねて走り回り、興奮がおさまらないことを不思議に思い、近くの僧院の僧侶に相談しました。
僧侶たちはコーヒーを煮出して飲むことで長い夜の祈りの際に眠気を防ぐのに役立つことに気付きました。
その後、コーヒーは健康にもよいことが明らかになって、次第に広まってゆき、やがてオリエントの他の地域にも広がっていきました。
※レバノンの言語学者ファウスト・ナイロニの「眠りを知らない修道院」(1671年)
「イスラム僧オマールの伝説」:イエメン
伝説の舞台は13世紀のイエメンの街・モカ。
人々から評判の良かったイスラムの僧オマールは、ある日領主により町を追放され、イエメンのオーザブ山に逃げ込みました。
オマールは山中で、食べるもの無く飢えていた時に、一羽の鳥が赤い木の実をついばんでいるのを見ました。
オマールは、その赤い実を口にしましたが、美味しいと言えなかったものの暫くすると不思議なことに疲れきっていたオマールの身体から疲労が消えみるみる力が蘇ってきて、気分もが爽快になりました。
その後、オマールを追い出した領主の町では、病気が猛威をふるった時に町の人々はオマールを追ってオーザブ山に分け入り、助けを求めました。
オマールは町の人のために祈りを捧げた上で、自分の身体に不思議な力を与えてた赤い実の煮汁を人々に与えたところ多くの人々が、病から回復しました。
この町は後にコーヒー豆の積み出し港として有名になった有名なモカの町であり、オマールは、この地名をとって『モカの守護聖人』と呼ばれるようになりました。
※イスラム教徒アブダル・カディの「コーヒー由来書」(1578年)記
コーヒーはトルコからヨーロッパ・世界へ
やがて17世紀に入ると、コーヒーはコンスタンチノーブルからヨーロッパに伝わりました。
1645年にベネチアにヨーロッパ初のコーヒーハウスが開店しました。
17世紀終わり頃にはインドやインド諸島へコーヒーの苗木が持ち込まれコーヒー栽培が始められました。
18世紀ころには中央アフリカと南米へ広がり、19世紀に入るとアフリカへと栽培地域が拡大されました。
ところで、バッハが「コーヒーカンカータ」を作曲し、コーヒーハウスでコンサートを開いたのは1730年頃です。
日本のコーヒーの歴史
コーヒーを最初に飲んだ日本人は?
日本ではじめてコーヒーが伝えられたのは鎖国政策下にあった17世紀後半の江戸時代だと言われています。
長崎の出島にオランダ人によって持ち込まれたされているコーヒーを飲んだ初めて飲んだ日本人は、出島のオランダ商館に出入りしていた通詞(現在の通訳)か蘭学者、遊女のいずれかではないかと言われています。
言うまでもなく江戸時代におけるコーヒーは、一部の人達しか味わうことのできない特別なものでした。
焦げくさくして味ふるの堪ず
江戸時代の中期と後期を代表する狂歌師・劇作家。御家人で幕府の官吏であった、太田南畝(太田蜀山人)が、著作「瓊浦又綴」(1804年)の中で、コーヒーを飲んだ経験(日本で初めての文書化された感想)を以下のように書き残しています。
紅毛船にてカウヒイというものを勧む、豆を黒く炒りて粉にし、白糖を和したるものなり、焦げくさくて味ふるに堪えず
コーヒーを薬として伝えたシーボルト
鎖国中の日本にやってきたコーヒーは、オランダ人が自分たちが飲むために持ち込んだとされています。
日本にコーヒーが伝わってから200年以上あとの1823年にフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトがオランダ商館医として出島にやってきました。
日本へ西洋医学を伝えた事で有名なドイツの医師であり博物者で出島の三学者の一人であるシーボルトは、著書『江戸参府紀行』に「200年以上、オランダの商人たちとも交流しているのにコーヒーがまだ日本に広まっていないことは驚きである」と書いています。
また「日本人は自分たちと交流する時、好んでコーヒーを飲む」とも言っています。
コーヒーを普及する為にシーボルトは、『薬品応手録』に「コーヒーは健康や長寿の効果がある飲み物である」旨を記載し、「コーヒーは健康に良い物」として推奨してきました。
蘭方医が日本でコーヒーを広めた
江戸時代に京都でコーヒーを広めたとされる医師は、蘭学者で蘭方医の広川獬(ひろかわ かい)です。
彼は、1800年(寛政12年)に刊行した「長崎見聞録」の中で、コーヒーについて記述し、その効能(コーヒーが食欲や活力の増進、消化促進、下痢止めなど)記載しました。
「かふひぃは脾を運化し、溜飲を消し、気を降ろす。よく小便を通じ胸脾を快くす。平胃酸、茯令飲等に加入して、はなはだ効あり」と、コーヒーの薬効を説明した
また、蘭学者で蘭方医であった吉雄耕牛(よしお こうぎゅう)も、コーヒーに関する知識を持ち、自宅でサロン「オランダ座敷」を開き、蘭学者たちにコーヒーを振る舞っていたとされていました。
尚、日本で初めてコーヒーを薬として処方したとも言われています。
複数の蘭方医の医師たちの活動によって、江戸時代中期には、コーヒーが日本において広まっていきました。
また、19世紀半ばは北方警備の為に北海道に送られた津軽藩士たちに寒気を防ぎ、湿邪を払う飲み物としてコーヒー豆が支給されたとの事です。
明治になり日本においてコーヒーを庶民も飲み始める
明治時代になると珈琲が本格的に輸入される始め、鹿鳴館時代(1883=1887年)にはハイカラな飲み物として普及し始めました。
1888年(明治21年)には東京下谷の西黒門町(現在の台東区)に、コーヒー主体とした日本で最初の喫茶店「可否茶店」が誕生しました。
1782年(天明2年)、蘭学者の志筑忠雄が訳した「万国管窺」という本の中に、「阿蘭陀の常に服するコッヒーと云うものは、形豆の如くなれどもじつは木の実なり」との記載があり、1797年(寛政9年)「長崎寄合町諸事書上控」の中には、長崎丸山の遊女がもらった物として「コヲヒ豆一箱。チョクラート」と記されています。
その後、明治41年に始まった日本からブラジルへの移民の多くがコーヒー農園で働いていたことから、ブラジル政府からコーヒー豆が無償で提供され、その豆を使ってコーヒーを低価格で提供するコーヒー店が繁盛したことで、コーヒーが庶民にも浸透していきました。
戦時中のコーヒー事情
戦時中、日本ではコーヒーは「敵国の飲み物」とみなされ、輸入が停止されました。そのため、コーヒー豆の入手が困難になり、代替品として、どんぐりやタンポポの根などを焙煎した「代用コーヒー」が用いられました。
戦時中、日本ではコーヒーは「敵国の飲み物」とみなされ、輸入が停止されました。そのため、コーヒー豆の入手が困難になり、代替品として、どんぐりやタンポポの根などを焙煎した「代用コーヒー」が用いられました。
戦時中コーヒー不足に悩まされ、どうしてもコーヒーが飲みたかった人々は、コーヒー以外の物で味を似せた代用品を生み出し飲んでいました。 灰汁を抜いたどんぐりを焙煎し抽出した、どんぐりコーヒーやたんぽぽの根っこを焙煎し抽出した、たんぽぽコーヒー。 キク科の植物チコリを用いたチコリコーヒーなどがあります。
コーヒー豆の種類
アラビカ種:コフィア・アラビカ(Coffea Arabica)
コーヒー豆の「アラビカ種」はエチオピア原産です。
世界のコーヒーの約70~80%がはラビカ種と言われています。
香り、酸味、コクに優れています。
高温多湿と霜害に弱い品種ですが南米やアフリカの高地をなどで栽培されています。
ロブスタ種
コーヒー豆の「ロブスタ種」はコンゴ原産です。
高温多湿のインドネシアなどで生産されています。
特有のクセがあり、主にインスタントコーヒーの増材料やアイスコーヒーなどに加工して使用されています。
リベリカ種
アラビカ種やロブスタ種に比べてあまり栽培されていません。
コーヒーの焙煎の度合い・保存方法
浅煎:焙煎時間が短く、酸味の強い味わい。苦味がなくさっぱりとしており、フルーティーな味わいがあります。
①ライトロースト(焙煎後約8分)・・・うっすら焦げ目がついており、黄色っぽい小麦色で、香り・コクが弱く、酸味が強いのが特徴であり、一般的に飲まれることはほとんどありません。
②シナモンロースト(焙煎後約9分)・・・シナモン色。苦味はほとんどなく、すっきりとした酸味が強く、コクや苦味はほとんどなく、まだ豆の青臭さが残っており、飲用には適さないが、酸味が最も強い煎り方であり、酸味好きなユーザーには好まれます。
中煎り:苦味・酸味のバランスが良い焙煎度。浅煎り豆に比べて色が暗く若干しっとりとしていて、コーヒー豆本来の味わいが出やすいので、レギュラーコーヒーの中で広く親しまれています。
③ミディアムロースト(焙煎後約10分)・・・薄い茶色で、さっぱりとしたまろやかさのある酸味と苦味がほんのり感じられ、アメリカンコーヒーに適しており、別名アメリカンローストともいわれるが、通常の珈琲はこのレベルから用いられます。
④ハイロースト(焙煎後約11分)・・・茶色で、酸味がだいぶやわらぎ、さわやかな酸味を残しつつ、すっきりした苦味や甘味が現れ、コーヒー特有のかおりが引き立ち、バランスがとれており、。一般的な焙煎度合いであり、やや浅めの「レギュラーコーヒー」として用いられます。
中深煎り:
⑤シティロースト(焙煎後約12分)・・・ハイローストより少し黒色。酸味と苦味のバランスが良く、コクのある苦味があり、最も一般的な焙煎度合いであり、レギュラーコーヒーとして持ち合いられています。深煎りの最初の段階であるシティーローストであり、近年は「エスプレッソ」に使う事もあります。因みに「シティ」という名称は「ニューヨークシティ」から由来します。
⑥フルシティロースト(焙煎後約13分)・・・黒茶色で、酸味が少なくなりコクと苦みとコーヒー独特の香りが強くなり始めます。コーヒーの芳醇な味と漂う香りも同時に楽しみたい人に好まれます。
深煎:焙煎時間が長く、香ばしくてビターな味わい
酸味が少なくなると共に、苦味が際立ってくる焙煎度合いです。また、こうばしい香りも一際強くなり始めるのでが特徴。酸味が強いコーヒー豆を深煎りにすると、すっきりとした味わいに変わる。コーヒー豆の色は濃い茶褐色~黒褐色。
⑦フレンチロースト(焙煎後約14分)・・・黒っぽい色で、コーヒー豆の内部から表面に油分が出て、テカテカり始め、苦味がかなり強くコク深い味わいで、酸味はほとんど感じず、コーヒー特有の香りや苦みが引き立ちます。カフェオレ、ウィンナーコーヒーなどミルクやクリームと掛け合わせるコーヒーに向いており、苦味が存在感を発揮します。
⑧イタリアロースト(焙煎後約15分)・・・焦げているように見える黒色で、油分でテカテカ光っていおり、焦げたような香り=スモーキーな香りと刺激的で重厚な苦味と深いコクが特徴です。本来はエスプレッソやカプチーノなどイタリアを代表するコーヒーの飲み方に適しています。
豆の挽き方
①粗挽き:コーヒーブレス(フレンチブレス)のようにコーヒー粉を浸漬する淹れ方など適しています。
②中挽き:
・ペーパードリップ(カリタ式:3つ穴) ・ネルドリップ ・コーヒーメーカーなどに適しています。
③細挽き:
・ペーパードリップ(メリタ式・1つ穴) ・マキネッタ(直火式エスプレッソメーカー)などに適してます。
④極細挽き:
・エスプレッソマシンなどに適しています。
コーヒー豆の保存方法
①常温:焙煎から2週間ほどは風味を保てます。
②冷蔵保存:常温よりも鮮度は長持ちします。
③冷凍保存であれば1カ月ほど保存可能です。
後書き
実は、私は1970年代後半に第三世界における珈琲並びにバナナのアグリビジネスとプランテーションの問題を知り、長年、珈琲とバナナは食していませんでした。
1990年代前半からPBのオーガニック(当時は海外認証のみ)・フェアトレードコーヒーを大手高級量販店や自然派メーカー卸部門などにも流通し始めましたが、21世紀の今では日本のどの地域でもオーガニック並びフェアトレードのコーヒーやバナナを比較的容易に入手する事はできようになりました。
その事で目利きが優れていて且つ焙煎技術が高い焙煎士の多くが、オーガニック並びにフェアトレードコーヒーを焙煎する事となり、美味しいとされるコーヒーの中にオーガニックコーヒーがラインナップされる事も珍しくなくなりました。
因みに私が珈琲を飲む事を解禁したのは、オーガニックコーヒー(当時は海外認証のみ)並びにフェアトレードを扱い始めた洛中の自家焙煎珈琲店と1980年代後半に関わった時からです。
その後、複数のオーガニック並びにフェアトレードコーヒーを扱うメーカー・団体等と2010年代前半にセミリタイヤするまで関わってきましたが、その中で、一番嬉しかったのは「東ティモール」産のオーガニックフェアトレードコーヒーと関わる事ができた事です。
コーヒーを飲むのをやめたきっかけは第三世界の問題に端を発したのは先に述べたとおりですが、当時、コーヒーの一大産地であった中南米の多くは軍事独裁政権であり、コーヒーの存在はフィリピンのバナナと同様に中南米の社会状況を象徴するものでした。
中南米で民主化を目指す人々の声、「今はコーヒーを飲まないで欲しい、そして民主化した時に、たくさんコーヒーを飲んで欲しい」が日本にも届いていました。
2002年に独立を果たすまで東ティモールはインドネシアの併合にされておりましたが、東ティモールの独立を願う人々から日本の一部のメディアに対して「独立の為に日本の人々の協力が欲しい」とメッセージが届き、その記事を目にしてから東ティモールの事をいつも気にするようになりました。
セミリタイヤして、自らオーガニックフェアトレードコーヒーの企画・販売に携わる事もなくなりましたが、自家焙煎珈琲の珈琲屋さんのメニューの中に「東ティモールコーヒー」を見る機会も増え、見るたびに飲むようにしています。
ところで、現代においては、オーガニック並びにフェアトレードコーヒーは街中で比較的入手できるようになりましたが、今なお食の安全性確保・第三世界を含む農業従事者の労働環境問題・環境の問題は解決できてはいません。
少しでも多くの人が、食に関して言えば、値段よりも生産プロセスなどを熟考した上で購入するだけでも結果として、食の安全性や食の安全性確保・第三世界を含む農業従事者の労働環境問題・環境の問題は解決していけるものと考えます。
自分の健康を考えて健康へのベクトルを進んで行けば、例え僅かでも他者の健康や地球環境が良くなって行くのは言うまでもありません。
マイクロプラスチック・ナノプラスチック~PFAS問題然り。
記事を作成する際に参考にしたサイト・出版物並びにイラスト・画像を利用させて頂いたサイト
- コーヒーの事典 監修 田口 護 (珈琲屋バッハグループ主宰)
- 珈琲の大事典 編者 成美堂出版 (特別協力:バッハコーヒートレーニングセンター)
- 手網でかんたんコーヒー焙煎 著者 岩田知也(玉屋珈琲店焙煎士)
- 社団法人 全日本コーヒー協会
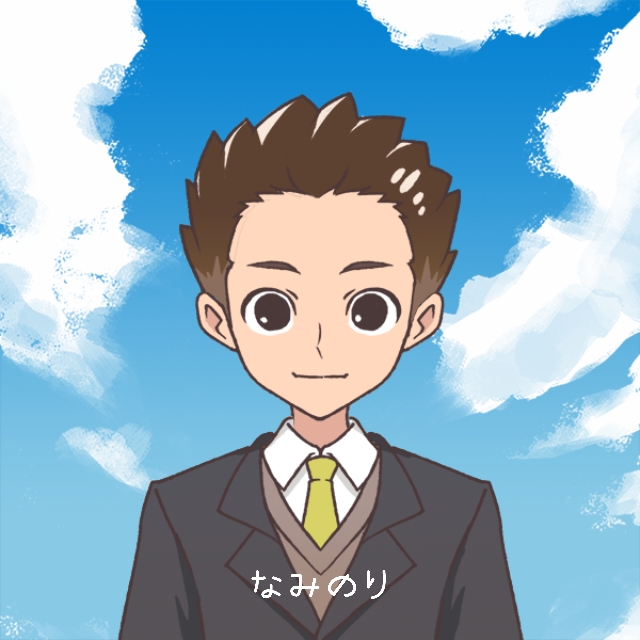

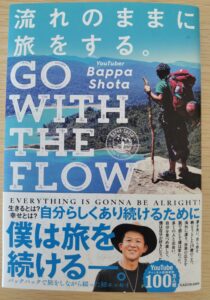
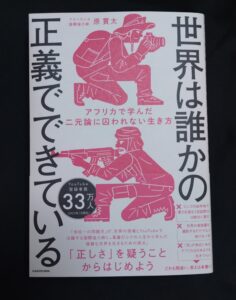

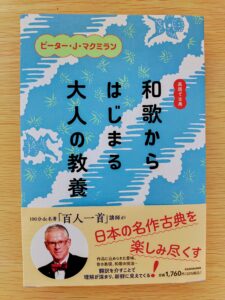


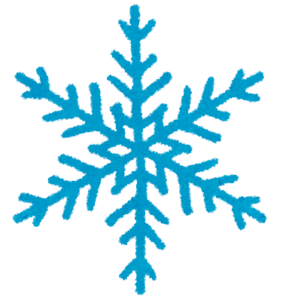

コメント